このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 区長の部屋 > 記者会見 > 令和6年度 > 区長記者会見(令和7年1月10日)
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月20日
ページID 22483
区長記者会見(令和7年1月10日)
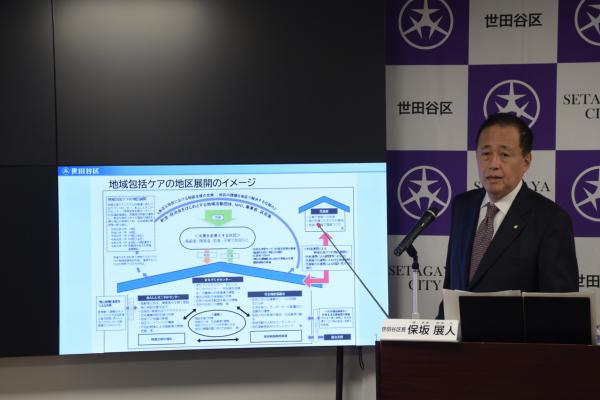
記者会見の様子
区長あいさつ
あけましておめでとうございます。令和7年最初の記者会見を始めます。
最初に、こちらの文字は「水遠山長」(水遠く山長し)という言葉です。「川の流れはどこまでも続き、山は長く連なっている」という意味で、秋の風景を表す言葉です。本来、心穏やかに、非常に静かで、また空気の澄んだ自然に恵まれた状況を指していますが、アメリカのロサンゼルスで大変な山火事のニュースが流れており、日本でも、長い夏から短い秋を経てすぐに冬に突入するかのように感じられ、気候変動・気候危機の影響が現れていると思いつつ、この言葉を挙げました。令和4年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は終わりを見せず、大勢の双方の軍人だけではなく、ウクライナの民間人も犠牲になっています。加えて令和5年からの、イスラム組織ハマスの奇襲に端を発した、イスラエルのガザ地区に対する空襲・地上侵攻は、約4万5,000人もの命を奪い、子どもたちは、直接の戦争の脅威に限らず、食糧の問題なども深刻です。国連機関も、活動を制限される中で、新生児が凍死するという痛ましいニュースもありました。そうした中で、ぜひ今年は戦火を納めるという年にしていけたらと思います。
令和6年を振り返ると、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)がノーベル平和賞を受賞し大きな話題になりました。広島・長崎での核による悲惨な被害を長年世界中で訴えてきた、被団協の皆さんの高齢化が著しいこと、そしていま、核戦争へのブレーキが弱まっていることが、昨年の被団協の受賞を決めたとも言われています。
令和7年は戦後80年となります。戦争がない状態で80年という歳月を何とか過ごしてきました。戦争で亡くなった国内外の犠牲者を追悼するとともに、その犠牲を繰り返さないという決意を次の世代につなげていく平和事業をしっかり取り組みたいと思います。また、新たな戦争への危機を止めることは私たちの責務であると考えています。
区では、昭和60年に平和都市宣言を行い、令和7年で宣言から40年が経ちます。また、戦後70年の平成27年には、区立平和資料館を世田谷公園内にオープンしました。引き続き、国の内外、軍人・民間人問わず戦争犠牲者を忘れることなく、戦争の経緯を検証し、体験を継承して歴史から学べる施設として発展させていきたいと思います。
次に、世田谷区民栄誉章についてです。この度、パリ2024オリンピック競技大会で金メダルを獲得された区内在住の2名の選手に、世田谷区民栄誉章を授与します。
まず、柔道男子66キロ級、阿部一二三(あべひふみ)選手です。もう1名は、レスリング女子フリースタイル53キロ級、藤波朱理(ふじなみあかり)選手です。阿部選手は、東京2020オリンピック競技大会の際にも授与しており、2度目の受章となります。各選手には、後日、個別に賞状等を授与させていただく予定です。
次に、世田谷区名誉区民顕彰式・記念イベントを1月5日(日曜日)に、世田谷区民会館ホールで行いました。世田谷区名誉区民として、新たに桑島俊彦氏、本夛一夫氏、横尾忠則氏の3名を顕彰しました。名誉区民である松任谷由実氏にもサプライズで駆けつけていただき、能登半島地震について応援していこうとスピーチをいただきました。
次に、能登半島での災害支援についてです。令和6年12月22日(日曜日)に、区の管理職や区議会議員の皆さんと区内5ヵ所で街頭募金を行い、計68万9,100円もの温かい気持ちをお寄せいただきました。区の能登半島地震災害支援金の総額は1月5日現在で3,928万3,885円です。お寄せいただいた寄附金は、第一次の寄贈として、令和6年4月に珠洲市と輪島市の両市長にそれぞれ500万円をお渡ししました。また、9月に豪雨による被害があったことから、10月に現地調査団を派遣した際に、第二次として珠洲市と輪島市にそれぞれ500万円、そして第三次として12月に珠洲市に1,000万円を寄贈し、計3,000万円をお贈りしています。能登半島地震から1年ということで元日以降、現在の能登半島の状況に関する報道がされていますが、大変難航していることが伺えます。過疎化の傾向が強まっていた中、地震による家屋の倒壊、そして解体や復旧などに着手し始めたタイミングで水害に見舞われました。区では令和7年1月6日(月曜日)より、珠洲市に職員1名を派遣しています。自治体間連携で、珠洲市・輪島市を中心に奥能登を支えていくことに取り組んでいきたいと考えています。
次に、世田谷版気候市民会議の実施についてです。気候市民会議とは、無作為抽出で選ばれた住民が、専門家等からの情報提供を踏まえて気候対策について話し合い提言する場です。すでに川崎市や杉並区などで開催されていますが今回、世田谷区でも開催します。1月26日(日曜日)から2月・3月に実施します。無作為抽出で選ばれた4,000名のうち、参加申込のあった248名から年齢層や居住地域、就労就業形態、居住形態などのバランスを考慮して55名の区民の皆さんに参加いただきます。これまでは気候変動にそれほど関心がなかったという人も含め、どんなことが区でできるのかを議論していきます。
続いて、令和8年度に本庁舎等に開設を予定している「区民利用・交流拠点施設」の試行イベント「区役所で遊ぼう」についてです。
現在、全3期に渡る本庁舎等整備工事における2期の工事中ですが、新しい本庁舎等のコンセプトの一つとして区民活動の拠点という考え方があります。行政や災害対策の拠点であるとともに、住民自身がホームグラウンドとして本庁舎を使用するという部分を強く打ち出した設計となっています。その区民利用スペースの多くは令和8年度中の完了を予定している2期工事で完成予定ですので、完成に向けた機運の醸成として、2月24日(月曜日・祝)の午前11時から、新庁舎東1期棟エントランスホール・ラウンジで、主に小学生を対象とした子ども遊び・ワークショップブースや、障害者福祉施設によるカフェなども出展予定です。こういった試みを通して、2期工事で完成する「区民利用・交流拠点施設」がどんな場所なのかPRしていきたいと思います。
発表項目
若手職員等による提案型プロジェクトチームについて
まず、「若手職員等による提案型プロジェクトチーム制度」についてです。
区では「新たな行政経営への移行実現プラン」に基づく取組みの一つとして、「職員の経験学習機会の拡充」に向けた取組みを推進しています。区の職員の年齢別構成は、35歳以下の職員が全体の40%を超え、今後さらに若い世代が増えていくことが想定されています。団塊の世代の退職などを経て、区職員の平均年齢が下がってきています。組織自体は過去の事例を手本に継承していく部分が多い状況ですが、若い世代ならではの柔軟な発想を発揮してもらいたいと考え、職員が希望するプロジェクトチームに参加してもらう取組みを開始したものです。令和6年度は、9つのプロジェクトテーマについて、参加を希望した32名の職員をメンバーとして、各テーマの担当所管と一緒にチームで動いています。
職員採用説明会を改革できないか話し合う、また、ドローンの活用検討やデジタルツールを活用した業務改善推進(DX-lab)等のプロジェクトがあります。プロジェクト活動では、他自治体の事例の視察や、専門家を交えたミーティング、魅力発信PRに向けたインタビューや動画撮影、地域イベントへの出展などを行っています。街中に入って、若い世代の職員自身が考えて進めていくプロジェクトをしっかり推進していきます。
労働報酬下限額の改定について
区では、平成27年4月1日に世田谷区公契約条例を施行し、令和7年で10年が経過します。
賃上げなど適正な労働条件を確保し、また、地域での事業者が正当に評価されるように、入札制度の改革も含めて、経営者側・働く側双方において好循環を創出していこうというのが公契約条例です。「労働報酬下限額」は聞きなれない言葉かもしれませんが、予定価格が3千万円以上の工事契約、2千万円以上の工事契約以外の契約(委託等)で適用される金額で、令和6年度では1,330円を遵守するようお願いしています。罰則等はありませんが、施行から10年を振り返ってみると多くの契約で守られています。他の賃金や、区との契約事業者以外の地域、近隣への波及もあり、賃金の底上げというのが出来てきたのではないかと思います。
公契約適正化委員会からの意見書を踏まえ、令和7年度に適用する労働報酬下限額を現在の1,330円から130円引き上げて、1,460円とすることとしました。1か月に換算すると約2万3,000円の引上げとなります。工事契約については、公共工事設計労務単価の各職種以外の労働者としていますが、工事では、専門技能が必要となるような職種それぞれに設計労務単価が設定されていることから、それ以外の労働者としています。1,460円という金額は都の最低賃金を大きく引き離す上げ幅となります。労働報酬下限額を通して、適正な労働条件によって雇用を支え、地域内・外、そして全国に波及していくことを期待しています。今回の引き上げにより、正規・非正規を問わず、区の公契約に従事する労働者の最低賃金は底上げされることとなります。
また、令和4年度より、世田谷区建設工事総合評価入札を試行として実施しています。労働賃金を上げると同時に、事業者側としては入札のあり方を検討してほしいとの声が以前から強くありました。区の場合、総合評価方式の評価項目の中に公契約評価点を設けました。賃金支払いの状況やワークライフバランス、労働安全衛生、男女共同参画などにおいて点数化し評価するものです。その結果、価格が高い方の事業者が総合評価で上回り落札するということも既に起きています。区としては、事業者の経営状況や事業内容をしっかり把握した上で事業者を選定しています。また、ダンピング防止の観点から変動型最低制限価格制度も導入するなど、公契約条例を通して、地域の事業者と働く方々の環境改善につなげています。
世田谷版地域包括ケアシステム10年の取り組みについて
国が推進する、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制、地域包括ケアシステムの構築について、区では10年前から取り組んできました。
区内には現在、各地区28ヵ所にまちづくりセンターがあります。10年前の開始から少しずつ実施場所を増やし、平成28年には地域包括ケアの地区展開として、まちづくりセンターにあんしんすこやかセンターと社会福祉協議会の三者がお互いに連携して役割を担うものとして、三者連携を開始しました。令和4年5月からは、子ども児童福祉の観点から児童館を加え、四者連携を実施しています。
介護保険制度はわかりにくいところもあり、例えば午前中にベッドから落ちて立てなくなってしまい、急に介護の必要が出てきた場合にもどこに相談すればいいか分からずに以前は半日から1日を要していたような事例もあります。現在は、福祉の相談窓口として、まちづくりセンター内に設置されているあんしんすこやかセンターにアクセスすればいい、ということが認知されてきています。また、午前中に電話すると、夕方頃にはあんしんすこやかセンターによる介護認定手続きなどの相談ができるようになってきました。92万の人口を擁し、高齢者の方も19万人近く住まわれている中で、いつ何があるかわかりません。その時に、相談する窓口はどこだと右往左往しない仕組みというのが、この地域包括ケアの地区展開になります。自治体での地域包括ケアの取り組みはそれぞれ異なるため、こうした地区展開はどの自治体でも実施しているようで、実施されていません。区では、自転車や徒歩でアクセス可能な、各地域に密着した1ヶ所の拠点で、介護保険についての制度を連携して受けられる仕組みを、10年かけて作りました。同時に介護予防として、社会福祉協議会が様々な企画を実施しています。また高齢者の場合、精神的な孤立が非常に怖いですが、800近いサークル団体が、区内で活動しており、社会福祉協議会ではこれらのネットワークも管理しています。振り返ると10年ですが、年々相談は増えており、特にあんしんすこやかセンターへの相談が非常に増えています。縦割りの組織の硬直性を、28地区全てを横につなぐという仕組みが、この地域包括ケアの地区展開です。他に例がありませんでしたし、区としても相当の判断の上、実施してきましたが、実現は大変でした。こうした区の取り組みは、地域包括ケアのひとつの雛形として、厚生労働省のホームページでも紹介されています。介護保険に関して、地区の相談窓口にてワンストップで対応しますが、福祉分野は非常に範囲が広いため、当然全てに対応はできません。そのため、的確に窓口の連絡先をご案内し、場合によっては各まちづくりセンターからオンラインで、保健福祉センターなどに繋いでいます。区で地域という場合、世田谷、北沢、玉川、砧、烏山の5地域に分かれます。そのもとに、まちづくりセンターが28ヶ所あり、そこを地区と呼んでいます。地区展開とは、居住圏に非常に近いまちづくりセンターのエリア単位で、地域包括ケアを展開するということです。その中で、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、児童館の四者を中心に、地域包括ケア会議を開催しています。制度発足時と比較し、実施回数は約2倍に増加しました。団塊ジュニアの世代が高齢者となる2040年に向け、高齢者だけでなく、障害者福祉、児童福祉など、他分野も包括して支えていこうという、地域共生社会という仕組みが国でも叫ばれていますが、区は10年かけて「世田谷版地域包括ケアシステム」を構築してきたということを、ぜひ分かっていただきたいと思います。
地域に根付いた一例として、区内に有料高齢者施設などが新たにできる場合に、施設の方からあんしんすこやかセンターなどに施設の取り組みについてお話をいただきます。それなりの入居費を取る高齢者施設には、例えば1階にステージのような設備を整え、年に何度かクラシックの演奏など催しを行っている施設もあります。逆に考えると、催しがなければステージは空いており、空いているときには地域で使ってもらえないかという相談をいただくことがあります。そうすると、町会のこども祭り、またカラオケ大会をするといったことがコロナ禍前から始まってきました。
また、以前であれば、あんしんすこやかセンターは高齢者に関する福祉を実施しているため、例えば、介護の相談を受けるためにお宅を訪問した際に、その家庭に引きこもりで悩みを抱えている方がいると分かった時にもそのまま対応することはできませんでした。しかし今では、三者連携に基づき、区のひきこもり相談窓口にご案内するなど、包括的に区民の皆さんの複数ある悩みや福祉的な需要に応えていくことができるようになりました。
最後に、令和6年度地域包括ケアの地区展開報告会を行います。日本語を話すことができない外国人の高齢女性の病気の治療にどのようにチームで対応したかという事例や、地域の中で男性の孤立が目立つということで、男性を地域に引っ張り出そうと、関係をつくり男性たちの得意分野でイベントに参加してもらった事例など、区内28地区それぞれの取組みがあります。今回は時間の関係で一部の事例について報告します。
行政の現場において、介護などの困りごとは当事者になって初めて分かることが多くあります。当事者になって、分からないことで躓き、必要な支援が受けられないこともあります。都市化が進む中で、どのようにきめ細かく、対話し信頼をつなぎながら、福祉基盤をしっかり発揮していくか、難しい部分ではありますが10年積み上げてきました。引き続き、福祉の相談について、包括的に区民の皆さんの需要に応えていきたいと思います。
質疑応答
- 記者
会見冒頭で平和事業に言及されたが、戦後80年ということで高齢の戦争体験者からの継承は大きなテーマかと思うが、具体的に実施を考えている事業はあるか。もしくは、8月に向けてやっていきたいことがあれば伺いたい。
- 区長
世田谷公園の一角に平和資料館があるが、来園者からすると場所が分かりづらいように思う。入場者の拡大だけを追うわけではないが、所在が分かりやすいように何らかの手を打ちたいと考えている。また、被団協の田中氏の発言でもあったように、10年後、被爆体験を自分の口で語ることができる人がどれだけいるか。現在、区内の戦争体験というと、空襲から命からがら助かった子どもの頃の体験や疎開の体験を話していただける方がいるが、10年経つとそのような方々も非常に少なくなってしまうだろう。私自身も含め、直接体験していないなかで、どれだけ戦争体験を訴えられるか。そうした点は、特に前半の5年程度でしっかり取り組みたいと思っている。8月15日を一つの目途として、10年後に向けて、平和資料館の位置付けを新たにし、子どもたちが広島・長崎を訪問する機会を拡大するというような様々な取組みを検討しているところである。
- 記者
労働報酬下限額の改定について、工事契約と工事契約以外の契約でそれぞれ引き上げ額が出されているが、令和6年度と令和7年度とも両者の金額に違いがないが、あえて分けて記載する理由はあるのか。
- 区長
工事契約については、設計労務単価が示されている51職種の方々の金額であり、工事契約以外の契約については、それ以外の方々の金額としてお示ししている。
- 財務部長
わかりやすく一本化してお示ししても間違いではないが、工事契約とそれ以外の契約は、報酬設定の仕方が異なるため補足させていただく。工事契約は区長が申し上げた通りで、基本的には国が定める51職種は、設計労務単価として金額が決まっている。但し、この国の設計労務単価は公共事業の積算で使用するものであり、それ以上の賃金を払ってもらうよう国から示すものではないため、区が示す労働報酬下限額とは性質が異なる。そのため、工事契約における労務単価をそのまま区の契約で遵守するよう求めるのは国の趣旨にも沿わないため、労務単価の85%を下限額と定めており、それが区における51職種の労働報酬下限額となる。それに当てはまらない工事契約以外の方の労働報酬下限額も同じ金額になっている。
なお、報酬について公契約適正化委員会での審議において議論がなされたが、工事以外の契約については、社会状況等を踏まえて引き上げ額を検討している。一方、工事契約における51職種の設計労務単価については、すでに国が政策的に毎年引き上げている状況がある。それを踏まえ、区の労働報酬下限額をその単価の85%とするかどうかを議論いただいた。その51職種に該当しない方々は、工事契約以外の契約の場合と同様に1,460円とすることで審議いただいた経過もあり、今回の資料のように記載させていただいた。
- 区長
そもそも、労働報酬下限額がなぜ1,460円であるかだが、平成27年にスタートしたときに、区の高卒職員の初任給を時給換算した金額に追いつくようにしようとスタートした。年月を経るごとに、一時金を含んだ金額や特別区人事委員会勧告による引き上げ等にあわせて底上げされていった。このように、高卒職員の初任給の時給を追いかけて引き上げている状態である。
- 財務部長
金額の設定については、春闘や経済の状況等を諸々総合的に鑑みて審議会から答申いただく。その基本線の一つとして、同一労働同一賃金の考え方がある。区の仕事をやっていただくため、区で働く職員と同じ労働、同じ賃金だろうという考え方が根底にある。その中での最低ラインとして区の高卒職員の初任給をベースに揃えていこうと始まった。施行開始した当初は、目標金額が高かったため段階的に引き上げていこうと、まずは本給部分に追いつけるように設定した。その後一時金も含めた額を目指そうとなった。現在の目標額は時間給で1,970円に相当する。令和7年度において、現在の1,330円から一気に増額するのは現実的ではないので、5年程度を目安に段階的に増額していこうということで、令和7年度については1,460円と設定した。
- 区長
補足だが、区からの委託先に対してこの金額を出してもらうようにお願いしている以上、区が任用する会計年度任用職員にも当然実施している。
内閣総理大臣が企業に対して賃金を上げるよう言及されているが、公共事業自体に、物価上昇を踏まえた適正な賃金を設定し、罰則等を設けない中でも一定の効果を生んでいることにご注目いただきたい。
- 記者
公契約条例を踏まえた賃金アップなどの区の取組みについて、他自治体等にも広げていく考えはあるか。世田谷区の担当所管に伺った際、23区のうち13区に公契約条例またはそれに類するものがあるとのことだったが、例えば、特別区長会などにおいて、区長自身が制定を呼びかけていくといったことを考えているか伺いたい。
- 区長
公契約条例自体は、世田谷区が最初に制定したわけではなく、この間に13区まで広がってきた。特別区長会で全区での制定に関する議論をしたことはないが、私個人としては、都が発注する契約等でやってみてはどうかと以前から考えている。もっと言えば、国として底上げできないか問題提起していきたいと思う。具体的な部分を詰めている訳ではないが、そのような方向で発言していきたいと思っている。
- 記者
労働報酬下限額について、令和6年度の1,330円までは、先程言及のあった高卒職員の初任給という基準に向けて計算通り上げてきたということだが、増額幅等も踏まえて令和7年度は1,460円に留まっている。来年度の検討の際、仮に高卒初任給に変動がなかった場合、例えば令和7年度で上げきれなかった金額分をまとめて増額するのか、または段階を踏んで増額していくのかなど、どのように考えているか伺いたい。
- 財務部長
基本的な考え方は、同一労働同一賃金であり、区職員の最低ラインである高卒初任給の時給額を目標額に設定しており、それは令和7年度も変わっていない。1年では一気に増額することは現実的ではなく数年かけて追いついていく考えも同様である。今回の議論にあたっては、特別区人事委員会勧告が、人材確保のために初任給を意図的に大きく引き上げている状況があり、国も同様だが15%以上増額している。それを時給換算すると先ほど申し上げた目標額1,970円となる。ただ労働報酬下限額は、区が勝手に設定するのではなく、公契約適正化委員会で審議いただいている。その委員には学識経験者の方、労働者側、経営者側の代表の3者で議論されている。そこで適切な金額を審議いただいており、様々な情勢を鑑みて具体的な金額が示された。最終的に、期末・勤勉手当まで含めた時給換算額を目指していく考えは変わっていない。5年後の目標値に達するよう、1年ごとに目標値を均等に分けて設定した。来年さらに本給が上がる可能性はあるが、新たな上限の目標が見えてくる。審議においても目標値に向け、春闘や世間の状況、並びに人事院勧告等を踏まえて最終的に上げ幅を検討すべきと考えており、来年度においても同様に議論がなされると認識している。
- 区長
数年前、特別区人事委員会が区職員全体の給料を下げるという勧告をした。勧告は受け入れることができないとして、その際も区では労働報酬下限額を上げている。今後、最終的に高卒初任給に追いつくことを目標としていきたい。
- 記者
労働報酬下限額について、13区の中では最高額ということでいいか。
- 財務部長
自治体によって定め方が異なる。新宿区、北区、江戸川区は、世田谷区と同様に、職種ごとではなく一律で金額を設定しているが、その中で世田谷区はトップの金額である。また、職種を限定して羅列した上、一律の金額であるような定め方をしている区もあるが、その中でも世田谷区が令和6年4月の段階ではトップの金額である。ただし特定の職種によっては、この金額を超えている区もある。
- 記者
企業によっては人件費が1割近く上がるため、頭を悩ませるポイントにもなるかと思う。このことについて区の考えはあるか。
- 区長
公契約適正化委員会において、事業者側の委員の方から、賃金を上げるとしても、事業者側の条件も呑めなければ継続できないという声もいただいている。事業者側と労働者側を含めて、可能な金額であるか議論の上で決定している。
- 記者
企業にとって労働報酬下限額は強制ではないと思うが、総合評価方式で適正価格の支払が評価されていることが、守る動機づけになっているのか。
- 区長
企業が作成したチェックシートを調査の上、払っていない場合は指導させていただいている。また現状として、労働報酬下限額を関係ないという態度で無視される企業は把握していない。企業が求人募集する広告において、大体は設定した下限額に沿って募集されていると見受けられる。同じ会社内で、区の仕事をしている人は時給が高く、他の現場で仕事をする人は100円安いなど、差をつけることは難しいのだと思う。信義則を大事にしており、罰金などは請求していないが、私は各企業、遵守していただいていると思っている。
- 財務部長
契約にあたってはチェックシートを作成してもらい、各業務に携わる従事者の賃金について報告を受けている。同様に、サブロク協定を結んでいるかなど、労働環境に関するチェックシートについても提出を求めており、課題がある場合、必ず改善の方向性など確認を実施している。委託する以上、下限額を前提にした積算をもとに予算を組み、契約額を予定額として設定をしている。また、来年度予算に間に合う期限のタイミングで、公契約適正化委員会の審議においても結論を出してもらっており、その間に周知もできるよう取り組んでいる。本制度を始めて、明らかに地域賃金自体は底上げができたという実感を持っており、経済が非常に厳しくなったとき、公共発注の賃金相場は、地域経済にとって大きな役割を果たすのではないかと思っている。
- 記者
応募職員の通常業務とプロジェクト業務の時間配分について、通常業務はそのままのため残業が増えるなど、プロジェクトに参加することで職員の負担増は発生するのか。
- 官民連携行政手法改革担当課長
本部職場の職務とともに、プロジェクトチームの所管課に対して兼務することとしている。活動時間は、就業時間内に週4時間という目安を設けている。集中的に議論するため、その週に多くの時間を割くといった事例もあり、数カ月間プロジェクトに参加する中で鑑みて、週4時間を超えないようにしている。どうしても集中的に作業が必要である場合、週4時間プラス超過勤務4時間、平均で週8時間は兼務としてプロジェクトチームに従事できる制度としている。
- 記者
提案型プロジェクトチーム制度におけるドローン活用検討プロジェクトについて、例えば特定区域においてはドローン規制をある程度緩和するなど、区民が一定のルールのもとに、自身のドローンを飛ばすことができるなど検討しているか。
- 区長
大規模災害時などに、ドローンを飛ばして被災状況を把握するなど考えている。規制緩和については、法令の関係などもあり非常に難しいところではあるが、まず職員の提案に注目して、なるべく実現するようにしたいと思う。
お問い合わせ先
政策経営部 広報広聴課
電話番号:03-5432-2008
ファクシミリ:03-5432-3001
