このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 区長の部屋 > 記者会見 > 令和6年度 > 区長記者会見(令和7年2月7日)
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月18日
ページID 23087
区長記者会見(令和7年2月7日)
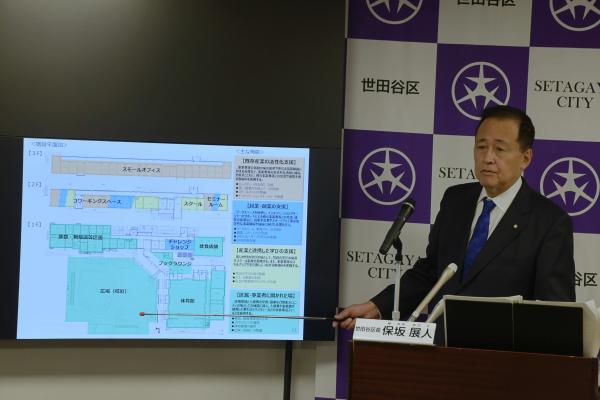
記者会見の様子
予算案概要:令和7年度当初予算(案)~『 学習する都市』 推進予算~
世田谷区の令和7年度一般会計当初予算(案)の記者発表を行います。
まず、一般会計当初予算の金額は3,996億1,700万円で、「『学習する都市』推進予算」と名付けました。
『学習する都市』には、生涯学習、自治体や地域で学習する環境や計画を整えていくこと、区民が主体的に参画し、コミュニティの運営に知恵を出し合い相互に改善していくといった意味を込めています。
教育
はじめに、「『学習する都市』推進予算」ということで、教育についてです。
まず、区で進めている教員の働き方改革の取組み状況について紹介します。世田谷区教育委員会において、「学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)」をとりまとめました。教職員へのアンケート実施により、日々の学校生活や働き方において何が悩みかを調査し、教員の1日の働く時間を分析して、子どもたちとのコミュニケーションをとる、対面する時間を増やそうという趣旨で対策案をまとめています。例えば、新人育成・緊急対応の強化のための区独自教員の配置や小学校高学年における教科担任制の導入、配慮を要する児童・生徒への支援の拡充、学校徴収金事務の負担軽減などが挙げられています。
最初にご紹介するのが、「区独自教員の配置による教育の質の向上」です。(予算額3,345万円)
現在、区立学校の教員の約3分の1が採用6年未満の20代の教員です。経験が浅い中で様々な困難に直面することがあります。学級運営がうまくいかずに気持ちが落ち込んでしまう、また、病気休暇等により学校に出勤できない状態となる教員もいます。そうした場合、他の教員や副校長等が授業に入るなどカバーしますが、結果的に学校運営に支障をきたしてしまうという状況が散見されます。
それを見据えて、区では令和7年度より、小学校を対象に、配置先の学校を固定しない教員を「学級経営支援教員」として配置します。学級運営や学校教育のレスキューチームのような形で、困難が生じてきたときに支援に入ります。小学校2校から3校に1人程度の配置とし、令和10年までに24人まで増やしてまいります。また、都が令和10年度までに12学級以上の小学校で高学年における教科担任制を実施することに合わせて、区では、令和7年度から小学校2校において、教科担任制を担う専任の区費講師を加配し、教科担任制を先行して始めていきます。小学校の教員はあらゆる科目の準備をしなければいけないため、教科担任制を担う区費講師の加配により、教員の授業面での負担を減らしながら、授業の質の向上を図ってまいります。
次に、「学びの多様化学校等の開設準備」についてです。(予算額7億4,595万円)
区では、不登校生徒への支援策として、令和4年4月に、学びの多様化学校(不登校特例校)「ねいろ」を世田谷中学校の分教室として開設しました。区ではこれまで、不登校の小・中学生の心の居場所であるほっとスクール(教育支援センター)を区内3か所に配置するなど、様々な支援をしていますが、不登校児童・生徒が増え続けていることもあり、なかなか追いついていない状況です。そこで、令和8年4月に新校として、旧北沢小学校跡地において、学びの多様化学校を開設する基本計画案を取りまとめました。この学校では、基礎的な学習内容の定着を図りながら、芸術や文化、科学などを中心に、生徒の興味・関心を引き出しながら学びを深めていくといった多様な学びを実践するため、これまでにない教育課程による教育を行います。また、気軽に体を動かせる「プレイルーム」や座り心地の良いソファーなどを用意した「リラックスルーム」を設けるなど、ストレスなく学べるような環境をつくっていきます。新設する学びの多様化学校は中学生を対象として1学年20人を定員としていますが、3階建ての校舎の中で、2階部分に定員35人のほっとスクールを併設します。多様化学校では様々な学習プログラムを実施しますが、ほっとスクールは学校ではなく、子どもたち一人ひとりに合わせて関わり支援する場です。この2つを同じ建物でスタートさせることには大きな意味があると考えています。ほっとスクールも令和8年4月に開設し、2階部分で学びの多様化学校の教職員とほっとスクールの職員がともにミーティングをしたり、子どもたちが一緒に交流したりすることも考えています。現在、旧北沢小学校で行われていて、小学生の放課後の居場所・遊び場として児童館の分館のような役割を果たしている「きたっこ(北沢子どもの居場所支援事業)」も同じ建物で実施していく予定です。児童館機能とほっとスクール、学びの多様化学校という三者が、三位一体で学校施設を使用するのは全国初の試みだと思います。開設まで1年となり、学習内容のプログラムや運営について準備を進めています。
続いて、「配慮を要する児童・生徒への支援の拡充(インクルーシブ教育の推進)」についてです。(予算額11億4,312万円)
この取組みの予算額は、令和6年度から6億5,676万円増額し、令和7年度は11億4,312万円と倍増します。区の教育の知見を生かしつつ、一人ひとりに応じた学びによって子どもたちの可能性を伸ばすことができる環境整備を進めていきます。
事業内容としては、大きく3点あります。1点目は、「(1)教育委員会及び学校の体制強化」です。インクルーシブ教育支援チームが区立小・中学校90校全校を訪問し、学校への助言等を行っていきます。
次に「(2)人的支援の拡充」です。小学1年生の学級担任を補助するエデュケーション・アシスタントを区立小学校全校に1名ずつ61名を新規で配置します。また、特別な支援が必要な児童・生徒の個別の見守りを行うインクルーシブ教育支援員を98人から151人へ、約1.5倍に増やします。
最後に「(3)教員の専門性・指導力の向上」です。教育委員会では「インクルーシブ教育ガイドライン」についてとりまとめました。障害があるなど様々な理由で支援や配慮を必要とする子どもたちに対して、インクルーシブとはどういうことか、どのように配慮して学校・学級を運営していくべきかなど、区としてインクルーシブ教育を一歩ずつ進めるために細かく議論し、当事者の子どもたちの保護者の方や教育について考える区民の皆さんとも議論した上で作成しており、令和7年3月に策定する予定です。ガイドラインの冊子は、教員一人ひとりに配付していきます。
次に、「小学校における登校時間前の児童の見守り」についてです。(予算額531万円)
小学校の登校時間は、保育園の登園時間より遅いということもあり、学校によっては開門の前に校門付近に児童が溢れてしまっている状態のこともあります。そこで、シルバー人材センターに委託し、教員の代わりに登校時間前に開門して、児童の見守りを行っていきます。まず、令和7年5月から、モデル校2校で開門時間を7時45分とし、学校敷地内で、子ども達が安全に待機する、また遊んでいるのを見守っていく事業を開始します。早く開門することで、通常なら教員に負担がかかるところですが、教員の負担軽減を原則に教育環境の改善をしていくことを踏まえて、シルバー人材センターへの委託としています。令和10年度までに、区内すべての小学校の開門時間を7時45分に統一することを目指します。
経済・産業・地域コミュニティ
「産業活性化拠点(HOME/WORK VILLAGE)の開設」についてです。(予算額1億878万円)
以前には、旧池尻中学校跡地において「世田谷ものづくり学校」が運営されていましたが、全面的にリニューアルして改修工事も行いました。この新たな拠点では、区内既存産業の再活性化や、新しい価値を創出する人材の育成など、区内産業のイノベーションを創出・加速し、若い世代の創業も含めて支援していき、地域経済の持続的な発展を目指す施設で、「HOME/WORK VILLAGE(ホームワークビレッジ)」という愛称になりました。令和7年4月に開設予定です。最先端の様々な新規事業にトライしていく大人の姿を見ることができる環境の中で子どもたちが学び、育っていく、そういった機能も内包しています。
施設の基本コンセプトは4つあり、「地域特性を活かした賑わいをつなぐ場」「職住近接のため多様な働き方の支援拠点」「多様な企業人材が新たな価値を創造する場」「未来を担う子どもへの新たな学びを実践する場」です。
どのような場所となるのかご説明します。まず、1階には、飲食・物販店等やチャレンジショップの区画を設けています。校庭は広場として、ゆったりとした空間を設けます。体育館ではスポーツイベントのほか、世田谷パン祭りやマルシェイベントなどにも活用していきます。そして、ブックラウンジとして、エントランスホールと一体化した本が置かれたコーヒースタンドを設置し、施設の顔となるような空間として整備します。
2階には、既存産業の活性化支援や起業・創業支援の区画としたコワーキングスペースとして様々な方が出入りし、インキュベーションマネージャーを常設して利用者の様々な相談ごとに対応し、他の事業者等との橋渡しも担うなど、事業者同士の交流・連携を促進していきます。スクール部分は、産業と連携した学びの支援を行う区画で、子どもたちの学びの場として様々なスクール事業を行っていきます。
3階は、既存産業活性化区画としてスモールオフィス、いわゆる貸し事務所の区画として15区画程度を整備します。4月末に供用を開始し、夏にグランドオープンを予定していますので、その都度お知らせしていきます。
次に、「せたがやPay」についてです。(予算額3億3,681万円)
沢山の方に活用いただいているせたがやPayについて、まずは令和6年度補正予算により、令和7年3月から4月に最大20%還元、5月に最大10%還元の物価高騰対策を実施します。その後、6月から令和8年3月まで最大3%を還元する区内経済循環推進施策を実施します。また、年末年始の反動を受けて消費が落ち込む令和8年2月には、最大10%還元の物価高騰対策を実施していきます。
せたがやPayは令和6年12月末時点において、ダウンロード数が42万4,918件、アクティブユーザー数は8万1,425件、加盟店登録店舗数が5669店舗、加盟店売上総額累計は334億1,989万円に達しています。地域限定通貨アプリとしてはかなり活用されているのではないかと思います。
せたがやPayにはスタンプラリー機能もありますので、それを活用したスタンプラリー事業の実施を予定しています。
1つ目に、インセンティブトライアル事業です。スポーツや運動に触れるきっかけづくりや、継続的な実施の機会につなげることを目的として、区立スポーツ施設や区内5地域の名所等を歩いて巡るスタンプラリーを実施します。スタンプの獲得、設定歩数の達成やアンケートに回答いただいた方、先着1,000人にせたがやPayを300ポイント付与します。
2つ目に、地域経済活性化スタンプラリーです。パン屋やカフェなどのグルメや魅力あるコンテンツをテーマにして区内全域に25か所から50か所程度のスポットによるスタンプラリーを実施します。参加をいただいた方から抽選で、せたがやPayコインや景品が当たります。
そして、せたがやPayを活用した新たな展開として、「地域コミュニティの担い手づくり支援事業」を開始します。(予算額3,371万円)
基本計画で掲げる「参加と協働」として、区民が自ら地域を支える存在として、主体的な参加への意欲を引き出すコミュニティづくりにつなげ、地域の担い手として活躍していただくことを目的とした取組みです。地域・人、福祉、子ども・子育てなど10分野を対象として、地域コミュニティを支える団体等が実施するイベントなどの運営を支援するボランティアの方へせたがやPayポイントを配布します。また、災害対策・防災に力を入れていくため、避難所運営訓練などに中堅世代の方にももっと参加していただきたいという想いから、こうしたイベントに参加する方に対して、今後の新たな担い手育成につながる場合に限りポイントを配布します。この事業を通して、潜在的に地域に関わりたいと思っている方に向けて参加のきっかけをつくっていきます。
災害・危機管理
災害・危機管理では、まず「在宅避難(マンション防災)の推進」についてです。(予算額3億9,678万円)
令和7年度は、集合住宅いわゆるマンション防災に力を入れ、地域防災力の向上を図ります。令和6年度、在宅避難の物品を備えていただくため防災カタログギフトを配布しました。ギフトの申込に際してアンケート調査を実施しており、マンション居住の方は戸建て居住の方と比較して、震災等が発生したら避難所に行くという回答が多く、戸建て居住の方のほうが、在宅避難の考えが浸透していました。そうした状況を踏まえて、マンション居住の方に対し在宅避難を意識して準備していただくため、共助を促す災害対策備品を供与します。1棟あたり最大30万円で、1,000棟程度のマンションに活用していただきたいと考えています。例えばAというマンションで申し込む場合、30万円以内であれば、選定いただいたポータブル蓄電池やキャリーカー、エレベーターチェアなどの災害対策物品を供与します。それぞれの集合住宅で必要な災害時の備えを区が広報することは非常に困難であるため、本事業は、申し込んだマンションの管理組合や自治会、場合によっては管理会社をネットワークとして構築して、在宅避難の意識を大きく改善したい狙いがあります。併せて、集合住宅を中心とした防災区民組織の新規結成を後押ししていきたいと思っており、マンションの代表者や管理組合の代表、場合によっては管理会社の方も含め、それぞれの地域に即した防災対策を、意見など情報共有するような場面を作りたいと考えています。
マンション防災については、3ステップでロードマップを描いています。ステップ1は、全区民を対象とした啓発動画の配信や、マンション居住世帯に対する防災啓発冊子の配布など、意識啓発に取り組みます。ステップ2は、各マンションで意見交換が必ず必要となるマンション防災共助促進事業とした30万円以内での災害対策物品の供与の実施です。ステップ3として、区民防災組織の結成や東京とどまるマンションへの登録をしていただくこととして、管理組合などがあまり活動していない場合は、管理会社にも声をかけてまいります。
続いて、「地域防災力の向上」についてです。(予算額2億6,466万円)
区立中学校の全生徒及び学校教職員用の防災ヘルメットを配備して安全確保を図るほか、教職員等による指定避難所の運営支援として、学校や地域で行う防災訓練の際に、生徒及び学校教職員がヘルメットを着用します。そうした姿を見てもらうことでも、防災意識を高めるきっかけにしていきたいと考えています。
地区・地域防災力の強化として、自助・共助の支援で、指定避難所への活動物品の配備をはじめ、訓練参加者に対して啓発物品を配布するなど、訓練のさらなる参加促進を図ってまいります。在宅避難の推進は、マンションの防災共助促進事業を通して、マンション防災をさらに進めるとともに、多摩川洪水等による水害時の避難所の暑さ対策として、避難所にスポットクーラーなどの配置を計画しています。行政拠点の強化では、拠点隊活動の経済支援や、支所の非常用電源の充実をしてまいります。
次に「住まいの防犯対策サポート事業」です。(予算額2億303万円)
昨今、闇バイトによる強盗事件や強盗未遂事件が次々と発生しています。区内でもいつ、このような事件が起こるかわからないという不安が非常に強く、区民の犯罪不安の軽減と住宅の防犯機能を高めていくため、住まいの防犯対策サポート事業に取り組んでまいります。例えば、録画機能付きインターホンや監視カメラ、或いは飛散防止用のガラスシートなど、4万円を上限に補助します。補助率は10分の10で、例えば10万円の設備を付けた場合には4万円の補助、4万円以下の設備をつけた場合は全額補助となり、地域の防犯対策を強化していく政策です。防犯カメラ、録画機能付きインターホン、防犯フィルム、ガラス破壊センサー、センサーライト、センサー付きアラームなど、様々な設備を組み合わせて防犯体制を強化できます。侵入者は、侵入に5分かかるとおよそ7割が、10分以上かかるとほとんど侵入を断念するというデータがあり、設備による防犯強化を呼びかけてまいります。申請期間は令和7年5月から令和7年9月末までを予定し、複数の品目を申請できますが、申請は1回でまとめていただきます。
子ども・若者
子ども・若者について、まずは「乳幼児短期緊急里親モデル事業」についてです。(予算額1,502万円)
出生して間もない赤ちゃんに虐待の危険性がある場合など、愛着形成が非常に重要な時期に、保育者が毎日輪番で変わるような施設よりは、家庭的に受けとめていただく里親のご家庭に預かっていただくのが最も望ましいと言われています。ところが里親に登録されている方がいても、今日、明日からいきなりということになると、乳幼児の緊急の一時保護が難しい場合があります。そこで乳幼児の一時保護が必要になった際、里親家庭でスピーディーな受け入れが可能となるように、あらかじめ月額10万円の待機料を支払い、緊急里親としてスタンバイをしていただくというスキームです。まずは本事業を進めるために、児童相談所や里親支援センターと連携し、緊急里親の新規開拓や受け入れ調整を進め、養育里親等の養育サポート等を行う里親等委託推進専門員を1名追加してまいります。同時にこの里親を知り、里親のなりてを増やしていくことも非常に大切ですので、里親制度を広く周知できるようバスの車体広告など行っていきます社会的養護の枠組みの1つとして、里親については仕組みや責任を十分知っていただいた上で、登録していただく必要があり、知っていただく機会を増やしていきたいと思います。
次に「子どもの意見表明と参加・参画の取組み」についてです。(予算額4,357万円)
子どもの成長や発達に応じて、子どもの意見の表明を聞いていくことが求められています。区の基本計画などを子どもたちに知ってもらい、考えたことをテーマに作成した作文や動画を募集して優秀作品を表彰する「キミのためのイマ・ミライ動画作文コンテスト」を実施して、子どもたちの意見を聞く機会を作っていきます。そして、9歳から14歳の小学生、中学生を対象とした世田谷区子どもの声アンケートを実施します。また、毎年、区政において重要な区民の意向調査資料としている区民意識調査では、これまで対象年齢18歳以上だったところを15歳以上に引き下げ、高校生世代以上の声も区民意識調査の中に含めていきます。また、若者が地域に関わっていく中で、多様な経験を通して、主体的に活動できるよう20万円を上限に活動費用を助成する「せたがや若者ファンディング」も開始していきます。また、すでに開始している「せたがや子どもFun!Fan!ファンディング」では、地域のために緑を増やそう、ベンチをつくろうなど、子どもたちならではの提案を子どもたちがプレゼンテーションし、審査の上、採用した団体に20万円を上限に助成していますが、対象団体を8団体から15団体に拡充します。こうした取組みで子どもたちの参加・参画を進めていくとともに、子ども権利委員会を設置します。子ども権利委員会は、日常的に子どもたちの人権や権利保障の視点に立ち、調査、評価、検証等を行う機能を持っています。また、子どもの権利に関しては、区役所内の庁内プロジェクトチームが中心となって、区民への普及啓発を図る事業を考えていきます。
続いて、「中学生・高校生世代の学習スペース等の確保」です。(予算額1,069万円)
希望丘青少年交流センターでの一番人気は学習室で、いつも満員です。試験前などは臨時でスペースを広げても埋まってしまいます。他方で、区民センターや区民会館などの区民利用施設では、夜間の利用率が非常に低い場所があります。一昨年に点検し、昨年から部屋が3つあれば1つを中高生が勉強をできるように開放を始めたところ、子どもたちに非常に好評であります。こうしたスペースを増やせるよう、代田児童館及び粕谷児童館の2か所、また図書館でも子どもたちが安心して勉強や読書ができるスペースを確保していきます。
最後に、「せたがや若者フェアスタート事業(世田谷区児童養護施設退所者等支援事業)」(予算額4,652万円)です。
児童養護施設、里親等の社会的養護の支援は、18歳以降になくなります。自立することになりますが、進学率も低く、これまで施設生活だった中で、いきなり社会に出て相談する人もおらず、仕事で様々な挫折をし、騙されてしまうというような被害もありました。この支援を充実させていくため、対象の範囲も広げていきます。
まず、世田谷区児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金について、ふるさと納税における区の流出額は大きいものですが、平成28年度から開始したこの事業では、段々と皆さんからいただくご寄附が増えています。寄附金額の増加に伴い、給付型奨学金の給付上限を50万円に拡充し、年齢要件を23歳未満から30歳未満に拡充してきました。資格等取得支援や家賃支援なども実施しています。
今回、新たに開始するのは医療費支援です。年間3万6,000円を上限に、医療費にかかる経費の一部を助成します。このほか、拡充内容としては、家賃補助について月額3万円を上限に補助しているところを、やむを得ない事情がある場合に2年間の再受給を可として拡充します。また、賃貸住宅保証料を上限2万円まで補助します。そして、資格等取得支援の拡充として、上限30万円まで高等学校卒業程度認定試験を補助します。基金から約4,600万円を活用して行う今回の支援の拡充により、対象となる若者たちは105人程度まで広がることを見込んでいます。
健康・福祉
「福祉人材の確保・育成・定着支援事業」についてです。(予算額3億1,018万円)
区では、福祉サービス事業継続を支援していくために様々な支援をしてきましたが、資格取得費用の助成やキャリアアップのための研修受講料の助成といった人材育成に関する取組みもきめ細かく行っていくとともに、定着への支援として、訪問介護事業所等の声を受けて電動アシスト自転車等購入費用の助成を実施します。
次に「世田谷区介護事業者経営改善支援事業」についてです。(予算額3,500万円)
報酬改定等の影響で経営状況が厳しい中、介護事業所の経営改善に向けてコンサルタントを派遣し、伴走型で支援していく制度を設けます。
続いて、「犯罪被害者等支援事業」についてです。(予算額2,505万円)
現在、「世田谷区犯罪被害者等支援条例」の令和7年4月の制定に向けて準備を進めており、犯罪被害者等に対して様々なきめ細かい支援をしていきます。相談に関する支援はもちろん、遺族弔慰金や遺族子育て支援金、重傷病支援金、性犯罪被害者支援金といった経済的支援、そして、転居費用助成や一時ホテル等に逃れる際の宿泊費用助成支援といった住居に関する支援、さらに、日常生活への支援として、配食サービスや一時保育・預かり費用助成、修学費用助成、就労準備費用助成なども実施します。そして、性犯罪被害を受けた方への緊急的支援も盛り込んでいます。こうした支援を実施するために、「(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援等基金」を創設して寄附を募っていきます。
次に、「困難な問題を抱えた女性への支援」です。(予算額2,069万円)
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、女性相談窓口の改善、そして、若年女性が安心して過ごせる居場所を提供していくため、民間団体等への補助を行っていきます。また、中高年の女性への支援として、経済的な困窮への支援体制の強化を、男女共同参画センター「らぷらす」を中心に進めてまいります。
次に、「医療的ケア児・重症心身障害児(者)の受入れ促進」についてです。(予算額1億5,796万円)
区では、放課後等デイサービスでの受入れ促進のために、夕方の受入れや送迎費用の助成を独自に行っています。今後も、医療的ケア児の居場所や、放課後等デイサービスの運営が継続できるようさらに後押ししていきます。
パートナーシップ10周年
次に「パートナーシップ10周年」についてです。(予算額293万円)
「世田谷区パートナーシップ宣誓」は、令和7年11月で制度開始から10年になります。10周年を記念して、シンポジウムの開催や事業の振り返りなどを通じて、制度全体の点検・改善のきっかけとなる1年にしていきたいと思います。
せたがや未来の平和館開館10周年
続いて、「せたがや未来の平和館開館10周年」についてです。(予算額1,009万円)
区立平和資料館も開館10周年を迎えます。戦後80年でもありますので、かつての戦争に日本がどう向かっていったのか改めて振り返るシンポジウムや、記念誌も発行します。そして、常設展のリニューアルのほか、施設名のサインを一新していきます。
人材育成の取組みの強化(人への投資)
最後に、「人材育成の取組みの強化(人への投資)」についてです。(予算額3,419万円)
まず、人事行政の現状をお伝えします。特別区職員採用試験の事務職において、平成26年には約1万3,000人であった受験者が令和6年には約半分の6,800人となり、最終合格者数は1,700人であったのが3,000人となっています。
そうした状況の一方で、世田谷区の普通退職者数は平成30年と比べて2倍となっており、特に若い世代での退職が目立っています。
こうした現状から4つの課題を整理しました。「キャリアサポート体制の整備」「管理職のマネジメント力向上に向けた体系的育成手法の構築」「行政実務能力の底上げ手法の整備」「未知の課題に対処するスキルの向上」です。
これらの課題を踏まえて、人材育成の強化につなげるための主な事業を4つ行います。「(仮称)おしごとライブラリの発信」「管理職のマネジメント力の向上」「提案型プロジェクトチーム制度・政策形成能力向上ゼミ」「海外派遣研修の実施」です。このような取組みを通して、優秀な人材が流出しないよう、また職員の更なる成長促進に向けて取り組んでまいります。
質疑応答
- 記者
学びの多様化学校について、学校法人という形での設立は23区初ということだが、学びの多様化を公の教育が実施する意味を、区長はどのように考えているか。
- 区長
学校教育については常に様々な意見があるが、日本は、1980年代に経済大国と評価され、正確かつ精緻な工業製品を大量生産する基盤的な力を、学校教育が対になって生み出してきた。製造業が後退し、情報産業などが前に出てきている現代社会において、改めて教育のあり方が問われている。オルタナティブ教育を実施する私立校が続々と設立されており、例えば、通学するため東京から他道府県へ転居する。また、特徴ある教育を実施している海外へ行くことを選択するなど、いずれの場合もお金がかかる。そのため、公立学校で新しい学びのあり方にチャレンジしていく学校が必要であると考えている。既存の学校で居場所がなく、それぞれの理由により学べない子どもが1,500人ほどいる。学びの多様化学校は一条校といい、学習指導要領に準拠した運営を行うが、特例校のため、午前は学科、午後は総合的学習という転換をすることもできる。学習指導要領を尊重しつつ工夫して、子どもたちがここで学べてよかったと実感し、内側の可能性に気がつくような場所にしていく。こうした手法で開拓した学びのあり方について、そのスキルを区内の全校に波及させていく役割も、教育委員会では考えていると聞いている。まずは1か所、旧北沢小学校の跡地に学びの多様化学校、そしてありのままを受け入れて様々な学びを提示していくほっとスクール、児童館機能を併設してスタートすることで、今、区の教育で対応しきれていない子どもたちに対し、しっかり受けとめていくことができるだろうと考えている。
- 記者
学びの多様化学校は、卒業資格を得られる認識でよいか。
- 教育総合センター長
中学校を卒業したことになる。現在ある、学びの多様化学校分教室「ねいろ」でも3年ほど実践を続けており、ほとんどの子どもたちが高校に進学している状況である。
- 記者
区長は2年前の選挙の際、公立学校のオルタナティブスクールを検討したいと言及していたが、かたちを変えて、今回の学びの多様化学校となったという理解でよいか。
- 区長
オルタナティブというのは「代わりとなるもの」という意味。子どもたちのありのままを受けとめるほっとスクールという居場所についてはすでに区内3か所に設置している。一方で、子どもたちが興味を持ち、熱中して学べるような芸術、科学、場合によってはジャーナリズムなどの分野について、区内にある大学や第一線で活躍されている方々の力を借りて子どもたちが学ぶことで、視野が開けて、自分自身が変わるという体験を学校でしてもらいたい。私立を選択する場合はどうしてもお金がかかる。そこで格差が生じてしまうことがある。そのため、公立学校の中で、平均的・標準的ではない、独特のカリキュラムを持った学びのあり方をぜひ実現したいという思いがある。オルタナティブ教育には様々な定義があり、これ自身がオルタナティブ教育の場という紹介はしていないが、文部科学省により不登校特例校の名称が学びの多様化学校に変わったことをより積極的に活かして、どこまで実施できるのかを追及して、子どもたちを受けとめていきたい。
- 記者
区独自に教員を採用配置することについて、実際に実施して検討すると思うが、再来年度以降も実施したい考えか。
- 学校教育部長
再来年度以降も続けていくつもりである。教員の時間帯別に必要な支援をしていくこととし、ある学校では教科担任制を導入して若手教員の支援も行うインクルーシブの支援員を配置する、また学校徴収金の取り組みを行うなど、長く指摘されてきた教員の働き方改革の変化を一挙に実施する考えである。
- 記者
各区の予算案では、例えば修学旅行の無償化や制服の無償化など、給付型が目立っているが、世田谷区は給付型とは一線を画し、教育を底上げするように、一人ひとりに合わせた教育を行っていくことを優先しているのか。
- 区長
例えば学校給食費の無償化は、複数の区で目指していく話が出たあたりで決断したが、給付が必要な部分は今後もあるのではないかと思っている。学校が楽しく学べる場であるためには、教員の雑事が多く、疲労がたまり子どもたちと向き合うことが難しい状態となっていることが問題だ。教育委員会で新たな機軸を打ち出すたびにレポートの作成も必要となり、現場の教員は忙しくなるというこの悪循環を終わらせたい。どうしたら教員の負荷を減らせるのか教育委員会が徹底して点検し、教員アンケートを全て分析して対策を考え、教員を雑事から解放することで負荷を軽減していく。例えば理科の実験キットなど、学習教材の支払い管理や集金、催促まで、現在は教員が行っている。こうした作業の一部を民間事業者へアウトソーシングし、その部分は教員が対応しなくてよくなることが教育環境の改善に繋がると期待している。また、現状では構造的に学校に過剰な負荷をかけ過ぎている。若い教員が自信を失い、職場に行けなくなるという手前で、緊急のベテラン教員を派遣することで支えていく。子どもたちが健やかに、元気に学んで成長する環境構築を全て学校、教員で受けとめているという悪循環を変えるため、多くの予算を計上した。
- 記者
ほっとスクールの取り組みについて、何が日本初であるか、改めて教えてほしい。
- 区長
ほっとスクールは、不登校の子どもたちの居場所として、子どもたちのありのままを受けとめる機能を有している。学びの多様化学校は、一般の学校とは異なるが、学習指導要領には準拠したプログラムを持っている。同じ校舎の中で双方の行き来があり、教員同士が交流する機能もある。さらにプラスして「きたっこ」という、いわば児童館の分室も入っているため、土日放課後は児童館目当ての地域の子どもたちも訪れる。日本初と申し上げたのは、このように三位一体でスタートするということで、日本で例がないと聞いている。
- 記者
総合支援型の学習、環境づくりが日本初ということか。総合的な施設として作られることが日本初ということか。
- 区長
学びの多様化学校は不登校特例校から改称された。ほっとスクールは、以前は適応指導教室と呼ばれており、適応指導教室は教育支援センターに変わった。呼び方が変わってきた中で、それぞれは各所にあるのではないか。
- 教育総合センター長
同じ場所に教育支援センターと学びの多様化学校がある施設は都内にもある。児童館の分室や乳幼児の施設、母親たちが集まれる場所を提供していくことを踏まえた総合的な施設としては日本初ではないかと考える。
- 記者
予算が前年比280億円増の7.6%増だが、区の人口が変わらない中、区民1人当たりが受けられる行政サービスの質は、7.6%充実するともいえると思う。一方でふるさと納税の流出が100億円を超えて問題視されていると思うが、それを踏まえても7.6%増ということは、ふるさと納税の悪影響が限定的なものとも見えるが、区長の見解を教えてほしい。
- 区長
ふるさと納税による直近の流出額は約111億円だが、次は約125億円の流出になるのではないかと見込んでいる。また、流出累計額は約580億円程度であり、これは現在、長い年月をかけて工事している区の庁舎建替工事費が収まる額である。その金額が流出しているということは、それなりのダメージがあったと考えている。一方、積立金を減らすわけでも、負債を増やすわけでもなく、これだけ予算が増えている理由は、財政上の努力と同時に、投資を非常に限定しているためである。現在、建設工事費が非常に高くなっているが、学校改築に集中しようとしており、大型建設工事は今のところ庁舎の建替えに限られている。近年、所得の高い方々が流入したこともあり、税収が上向きカバーできた部分があると思う。景気は循環するため、土地や株の上昇トレンドばかりではなく、景気がダウンして経済が厳しくなれば、ふるさと納税自体は逆に増えると思う。その影響は、潜在的に大きな困難を抱える要因になっていると考えている。
- 記者
他区では大規模な開発や建設事業に影響が出ている状況もある中、世田谷区の考え方としては、区立学校の改修・改築といった不可欠なものにある程度絞り、大きな事業としては本庁舎等の工事のみで、現時点で大きな影響が出ているものは無いということか。
- 区長
影響はこれから出てくるのではないか。学校の改築について言えば、区長就任時と比較して1校当たりの金額の増加に驚いている。区立学校の数は多く、改築等を毎年3校ペースで行う計画であり、金額面などを常に見通しながら計画を立てている。
- 政策経営部長
公共施設等総合管理計画において、令和6年3月の時点で、建物や道路、公園等の整備に年間740億円程度となる試算をした。改めて令和7年度に向けて試算したところ、年間870億円程度になると判明し、建築費の物価高騰等の影響が伺える。試算では、令和11年頃に、単年度で1,000億円を超えるような状況が見込まれ、学校改築を年間3校進めていくには財政的に厳しい状況であるが、やらなくてはならない業務であり、着実に進めていきたいと考えている。
- 記者
マンション防災の推進について、珍しい取組みなのか、またどのようなオリジナリティがあるか伺いたい。
- 区長
マンション防災について、車座集会等で各地域の皆さんの声を聞くと、災害対策に関する意見は必ず出ており、マンション等の集合住宅において、コミュニケーションが難しいといったことを聞いている。
- 危機管理部長
今回の取組みは、マンションの共助、協力関係づくりを促していくものである。他区では、エレベーターの閉じ込め対策としてエレベーターチェア等の配布、またマンションの自主防災組織に資機材を提供するといった取組みがあると聞いている。世田谷区としては、まずマンション内での協力関係づくり、共助を促していくために今回の取組みを考えた。他区で同様の事例は把握していない。また、都では東京とどまるマンションという制度がある。この制度は防災資機材の経費を補助するが、補助を受けるには防災マニュアル等を作るといった条件があり、マンション1棟丸ごと登録を受けるような取組みで、なかなかハードルが高い部分もあるのではないかと思っている。そのため、今回の区の取組みでは、できる限りハードルを低くし、共助の関係づくりを促進できるような取組みを考えた。
- 記者
今回の取組みは、分譲マンションを対象にしているのか。
- 危機管理部長
対象としては賃貸マンションも含めているが、管理組合がある、または管理会社が管理しているマンションの申込割合が高いのではないかと考えている。区内には、賃貸・分譲マンションを合わせて1万棟余りあるため、幅広く申込みいただける取組みにしていきたいと考えている。
- 記者
小学校における登校時間前の児童の見守りについて、試験的に始めている自治体もあり、朝の小一の壁対策というものかと思う。児童が開門時間まで外で待っているということも聞くが、世田谷区の状況を伺いたい。
- 学校教育部長
現在、区では各学校独自で敷地内に入れる開門時間を設定しており、学校ごとにまちまちである。各学校で、昇降口前や校庭に集まり、学年ごとに並んで待つといった取組みをしている。こうした受け入れでは当然、教員も出勤している。今回の取組みは、そういった役目をシルバー人材センターに委託していくものである。
- 記者
乳幼児短期緊急里親モデル事業について、これは都内初の取組みか。また、一般的な乳児院での保護ではなく、緊急里親で対応する意義について、改めて伺いたい。
- 区長
乳幼児期においては、愛着形成の点で、児童養護施設や里親、乳児院など社会的養護よりも、家庭的な環境の中で育てられた方が望ましいと言われている。ただ、今晩から急遽というような緊急性の観点から、これまで実現が難しい部分があった。
- 子ども・若者部長
大分市や福岡県、山梨県などでの取組みを参考にして進めてきた。現時点で、都内で同様の取組みを実施している自治体があるとは把握していない。
- 記者
学びの多様化学校について、現在の学びの多様化学校分教室「ねいろ」はどうなるか。
- 教育総合センター長
区は広く地域的な課題もあるため、分教室「ねいろ」も継続していきたいと考えている。
- 記者
区長として、肝いりの政策は何か。
- 区長
今日紹介したもの全てである。学びの多様化学校は必要だと思っているが、こうした学校の開設だけではない。学校環境の大幅な改革を上から押し付けるのではなく、現場の教員がしっかりと授業準備する時間を確保していくことを踏まえて、今回の「『学習する都市』推進予算」と名付けている。また、コミュニティに参画する観点でのせたがやPayの活用など、様々な意味で学習する都市という柱が立った予算案ではないかと思っている。
- 記者
現在、国政では103万円の壁の問題がある。どうなるか未定だが、来年度以降の区の財政への影響はいかがか。
- 区長
積立金もあり、来年度いきなり大幅に事業を削るようなことにはならないと思っている。103万円の壁の問題については、最終的にどうなるか不明だが地方の知事が皆反対されていた。178万円に引き上げられた場合に、区ではおよそ250億円程度の減収になるのではないかと試算している。加えて、100億円を超えるふるさと納税の流出もあるとなかなか大きな困難になる。こうした減収分について、地方交付税で補填されれば良いが、特別区をはじめ不交付団体はとてもたまらない。今後、どのように国の予算が修正されるのか、財源の補填がなされるのかといった点は我々の側から声を上げていかないといけないと思っている。ふるさと納税のように補填されないとなると、様々な事業が大きく影響を受けることになるため、これから常に発言していかなければならない問題だと思っている。
- 記者
他区の予算発表も取材しているが、教育委員会の取組みについてのボリュームのある資料が出てきて驚いた。今回の予算案について、教育委員会の努力が伺えるが、どのような部分が大変だったか伺いたい。
- 教育総合センター長
今、子どもたちが直面している課題に対して、取り組まなければならないことを一生懸命やろうと、教育長のもと、号令をかけて進めてきた。教員の働き方改革や学びの多様化学校、インクルーシブ教育といった項目を、うやむやにせず取り組めたと思っている。
- 記者
最後に要望だが、日本初、都内初などの取組みの独自性に関する表現を、先に資料に記載してあると分かりやすい。
- 区長
あまり自分で宣伝するのではなく控え目にしたいという部分もあった。聞かれれば答えさせていただく。
添付ファイル
関連リンク
お問い合わせ先
政策経営部 広報広聴課
電話番号:03-5432-2008
ファクシミリ:03-5432-3001
