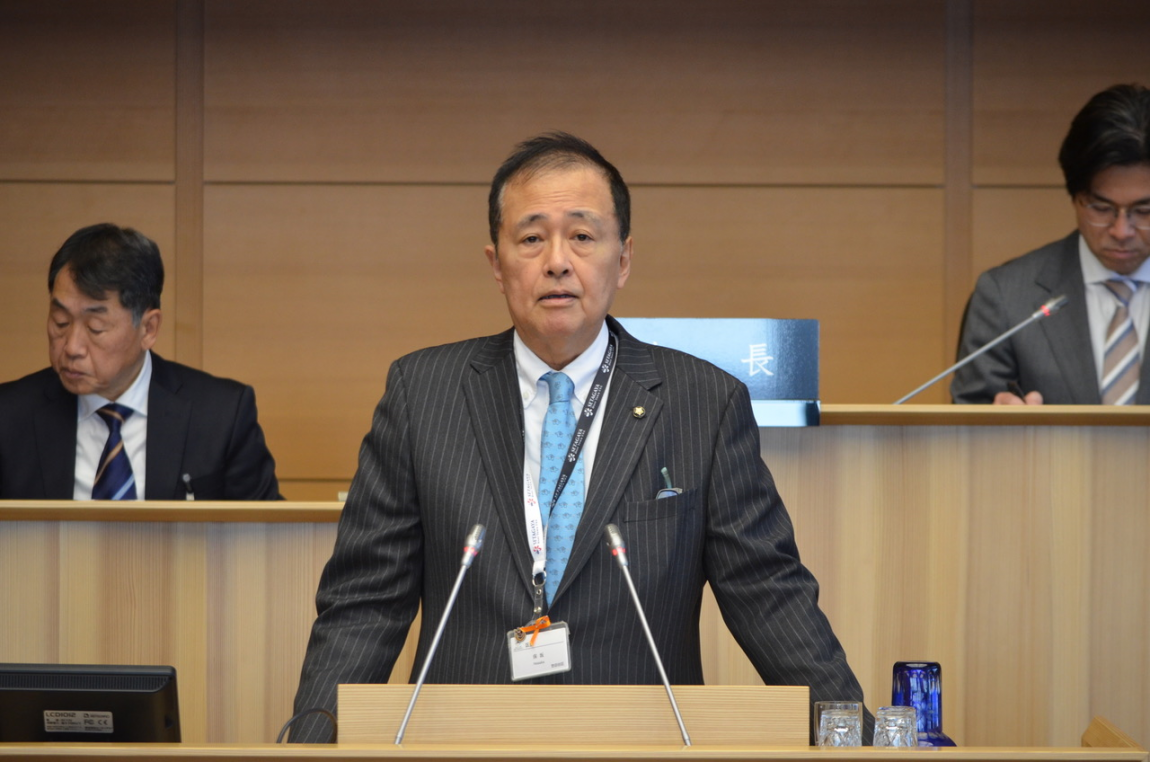このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 区長の部屋 > 施政方針 > 令和7年第1回世田谷区議会定例会区長招集挨拶
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月19日
ページID 23418
令和7年第1回世田谷区議会定例会区長招集挨拶
令和7年第1回世田谷区議会定例会にあたり、区議会議員並びに区民の皆様にご挨拶を申し上げます。
はじめに、犯罪被害者支援についてです。
この度、犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族が被った不利益の回復や軽減を図るとともに、犯罪被害者等に対して温かい支援のある地域社会をつくっていくため、「世田谷区犯罪被害者等支援条例(案)」を取りまとめました。
ある日突然に、誰もが犯罪による被害者やその家族、遺族になる可能性があり、犯罪被害に遭うことで、身体的な傷害や経済的な損失を受け、心身の不調などにより、生活が困難となることがあります。
この間、区では犯罪被害者支援をさらに強化するため、「世田谷区犯罪被害者等支援条例(案)」の制定に向けた準備を進めてきました。この条例では、犯罪被害者が速やかに生活を再建できるように、被害者本人への支援金の給付や、遺族への弔慰金、日常生活に支障をきたしている方への家事代行サービス費用の助成などについて検討を重ねてきました。
また、区の犯罪被害者等への支援の取組みを広く区民に知っていただくため、昨年12月15日に「世田谷区犯罪被害者等支援条例シンポジウム」を開催しました。第1部では、平成16年(2004年)に長崎県佐世保市で発生した「小6女児同級生殺害事件」の被害児童のお兄様にご講演をいただきました。この事件は、小学校の昼休みに教室内で同級生の女子児童からカッターナイフで命を奪われるという大変衝撃的な事件で、私も当時ジャーナリストとして現地を取材した経験を持っています。
講演では、当時中学生だった被害児童の兄が、親や学校関係者など周囲の大人から、妹に関わる事件について誰からも聞くことができず、長い間自分の気持ちを押し殺していた辛い経験を語っていただきました。続く第2部のパネルディスカッションには、平成12年(2000年)に発生した「世田谷一家殺人事件」の遺族の入江杏さんにも参加いただき、隣家の妹夫妻と子どもたちを同時に失うという深い悲しみと向き合いながら、残された者として、生きる姿勢についてお話しいただきました。
本条例に基づき、相談窓口の体制をさらに充実させ、専門の相談員が被害者に寄り添い、犯罪被害者の立場にたって、支援金の給付や配食サービスなどの生活支援を行ってまいります。また、今後の安定的な支援を続けられるよう「犯罪被害者等支援基金」を新たに創設し、犯罪被害者やその家族、遺族が安心して暮らせる地域社会の実現を目指して、全力で取り組んでまいります。
次に、世田谷区の地域包括ケアシステム10年の歩みについてです。
今から10年前に、超高齢社会の到来を前に、抜本的な福祉の構造改革を目指して「世田谷型」の地域福祉の実現に向けて動いてきました。
きっかけとなったのは、2025年問題でした。団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)以降に、医療や介護の需要がさらに増加する見込みとされていたことでした。本年がその2025年となります。
区においても、平成27年(2015年)10月1日現在の75歳以上人口は88,016人でしたが、令和6年(2024年)10月1日現在の75歳以上人口は108,511人となり、10年で2万人以上の増加となっています。介護が必要となる要介護認定者数は、平成27年(2015年)度末は37,659人でしたが、令和6年(2024年)度末には約43,000人となり10年で5,000人以上の増加となっています。
また、少子高齢化社会が進み、高齢者だけで暮らす世帯も増加しており、令和6年(2024年)4月1日時点で高齢者がいる世帯のうち高齢者だけで暮らしている世帯は7割を超え、そのうちの半数がひとり暮らしとなっています。
高齢者の介護を高齢者が行う老老介護や、家族などの介護のための介護離職など、事態はより深刻になってきています。福祉、医療、介護、住宅、また予防など、地域資源に依拠した地域包括ケアシステムが必要とされる状況となっています。
区は、これまで「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現」を目指し、公的サービスの充実とともに、区民による相互扶助や地域の活動団体等と協働した多様な取組みを進めてきました。平成26年(2014年)3月に策定した世田谷区地域保健医療福祉総合計画において、区の目指す地域包括ケアシステムは、区の地域社会の特性に鑑み、高齢者だけではなく、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など対象を広く捉え、また、支援を必要とする人だけのものでなく、元気な高齢者や学生など幅広い区民参加のもとで「世田谷版地域包括ケアシステム」として推進することとしました。
最大の特徴は、区独自の3層構造である地域行政制度に基づいた「地域包括ケアの地区展開」にあります。各地区に設置する地域包括支援センターをあんしんすこやかセンターと親しみある名称とするとともに、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会が、同一の場で、三者連携の仕組みを構築してきました。また、令和4年(2022年)度からは児童館を加え四者連携とし、子ども分野における地域資源開発にも力を入れています。
「世田谷版」の特徴は、徒歩や自転車などですぐに行ける区内28か所に「福祉の相談窓口」があることです。「介護」が必要になる時は、ある日突然やってきます。以前は家族が急に倒れ歩けなくなった時に、どこに相談すればいいのか、窓口を見つけるのも一苦労でした。今では生活圏に身近な地区の「福祉の相談窓口」に行けば、あんしんすこやかセンターで、ワンストップで手続きができ、必要な時には、まちづくりセンター、社会福祉協議会がそれぞれの守備範囲を横つなぎ、連携して対応してくれます。
地区で福祉課題が解決する取組みを「世田谷版地域包括ケアシステム」と名付け、令和6年(2024年)4月に策定した地域保健医療福祉総合計画では、基本目標を「世田谷版地域包括ケアシステムを支える基盤整備」として強化をはかっています。
「世田谷版地域包括ケアシステム」は、スタートから10年を経て、区民のニーズに寄りそう形で変容しています。国も区の取組みに対し、これまでの高齢者のみを対象としてきた地域包括ケアシステムに、障害者福祉や児童福祉などの他分野の相談窓口との一体的な設置や連携を促進していくことが重要である、との見解を示してきました。また、医療・介護・住まい・生活・社会参加の支援が必要な者は高齢者に限られず、経済的困窮者、単身・独居者、障害者、ひとり親家庭や、これらの要素が複合したケースも含め、究極的には、全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う「地域共生社会」の実現が、「地域包括ケアシステム」の目指す方向であると言及するようになりました。
「福祉の相談窓口」では、まちづくりセンターが地区の行政拠点となり、その上で、あんしんすこやかセンターを中心に、他の自治体においては地域包括支援センターとして、高齢者のみの相談を受けているなか、世田谷区では10年前の当初から、障害や子どもに関する相談も受けており、開始年度の平成26年(2014年)には101,146件だった相談件数は、令和5年(2023年)には185,931件と約1.8倍となっています。
あんしんすこやかセンターの職員が複合的な課題に区民ニーズを受け止めて動き、つなぐ体制がこの間で定着してきました。介護保険の相談で訪れた高齢者宅に、実は50代の引きこもりの息子さんがいるという事が分かった事例でも、スムーズにひきこもり支援に繋ぐことができるようになりました。
また、あんしんすこやかセンターだけではなく、「福祉の相談窓口」に行けば、社会福祉協議会が有する自主グループ活動を紹介することで社会的孤立防止や外出頻度の増加によるフレイル予防や介護予防につながります。
縦割りに横串を刺して連携し、協力して取り組むためには試行錯誤が必要でした。しかし、それぞれが歩み寄り、情報共有しながら進めてきたことで世田谷版地域包括ケアシステムのこの10年の集積ができあがりました。28か所のまちづくりセンターに配置した「福祉の相談窓口」を基軸とした「世田谷版地域包括ケアシステム」を深化させるために、5つの総合支所の保健福祉センター所長が、来年度より兼任で地域包括ケア担当参事を担うことにします。
今後、「世田谷版地域包括ケアシステム」の強みを活かし地域共生社会の実現に向けて強力に進めていきます。
次に、子ども条例等の一部改正についてです。
この間2年にわたり、条例改正に向けて検討を重ねた結果を、「子ども条例の一部改正(案)」としてまとめました。
今回の改正では、子どもの権利を明確に記載するとともに、権利の主体である子どもが、条例を自分のものとして受けとめ、活かすことができるよう、「前文」、「目標」、「子どもの権利」といった条文を子どもたちが考え、子どもたちの思いを生かした条例改正(案)としてまとめています。
条例の検討は中高生世代の子どもたちで構成する「子ども条例検討プロジェクト」において、大学生世代のファシリテートのもとで進めました。6月から7月にかけて開催した前期の検討会では、児童館や青少年交流センターなどで聴いた子どもの声や、アンケートの結果などを踏まえ、条文を一から考えました。
10月から11月にかけて開催した後期の検討会では、前期の議論を反映した改正条例(素案)を子どもたちにフィードバックするとともに、素案についての議会での議論や、パブリックコメントなどに寄せられた意見などを踏まえ、条文の表現を再検討しました。
条例改正(案)第15条には「子どもが参加・参画できる機会の確保と意見や思いの尊重」について記載していますが、普段からその機会を設けてほしいとの子どもの声を受けて、令和7年度当初予算案に「ユースカウンシル事業」を盛り込んでいます。身近に感じている課題や、区政課題について、子ども・若者に当事者目線で議論を行っていただき、意見を区政に反映していくことで、条例改正(案)の目標である「子どもの権利が当たり前に保障される文化をつくり、発展させ継承していく」地域社会を実現してまいります。
子ども条例の一部改正(案)に掲げる理念の実現に向けて、これを推進するために「子ども・若者総合計画(第3期)(案)」をまとめました。
「子どもが権利の主体として、一人ひとりの健やかな育ちが保障され、子ども・若者が、自分らしく幸せな今を生き、明日からもよい日と思える社会を実現する。」ことを目標に掲げ、子ども・若者の育ちと成長、子育てを子ども・若者や保護者だけの責任とせず、地域社会全体で支えるための取組みを推進することを「政策の柱」としています。
令和7年度当初予算案では、新たに子ども・若者基金を活用した、子ども・若者の主体的な地域活動への助成事業、悩みや困難を抱える若年女性の居場所事業、乳児期短期緊急里親モデル事業等を盛り込んでいます。これらの事業を通じて、子ども時代に自分らしさが肯定され、自分自身の声が周囲に受け止められるポジティブな体験や機会の充実を図ってまいります。
次に、児童養護施設退所者等への支援の拡充についてです。
区では、児童養護施設等を退所した若者への支援として、平成28年(2016年)にせたがや若者フェアスタート事業を開始しています。社会的養護の枠組みから巣立った18歳以降の若者たちが夢と希望を持てるよう、児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金を創設したところ、9年間で累計3億5千万円の寄附が寄せられました。この間、進学時の給付型奨学金、そして資格等取得支援、住まいの支援や家賃補助、居場所の提供等に取り組んできました。
一方で、施設等には入所せず、支援を受けながら家庭で生活を続けている子どもも、虐待による心の傷を抱え、大人になってからも被虐待経験に起因する生きづらさや心身の不調等に悩まされるなど、親を頼ることができず困難に直面している場合があります。
これまでは、対象を18歳以降に児童養護施設等を巣立った若者としてきましたが、環境の違いのみで支援が狭まることのないように改めます。具体的には、18歳より前に退所した者や、施設等入所経験はないが過去に虐待等を受け、児童相談所または子ども家庭支援センターの支援を受けたことがあり、現在親族からのサポートがなく困難な状況にある若者なども対象とすることといたしました。
あわせて、安定した生活基盤及び学び直しの保障のために、新たに医療費支援・高等学校卒業程度認定試験補助・賃貸住宅保証料補助を実施いたします。
これらの事業拡充に伴い、基金に寄せられた寄附が着実に児童養護施設退所者等の社会的自立に活かされるように、本定例会へ条例の一部改正案を提案します。
また、経済的支援だけでなく、相談支援機関である「せたエール」による継続的できめ細やかな伴走型の支援を行い、親を頼ることができない若者が同じスタートラインに立ち、互いに悩みや夢を持ち寄りつつ、相談ができる場も継続していきます。
次に、中高生世代の学習スペース(居場所)の確保についてです。
青少年交流センターの学習スペースや、一部の区立施設は、多くの中高生が夜遅くまで自習・勉強する場として活用されています。
昨年度、区が実施した中高生世代への居場所に関するインタビュー調査でも、「勉強や自習ができる環境を整えてほしい」という回答が多い結果となっており、「学習スペース」のニーズの高まりがあります。
これを踏まえ、令和7年(2025年)4月から試行実施として、2箇所の児童館で運営時間外の夜間帯に学習スペースを開設します。
また、区立図書館でも、中高校生世代が互いに交流できる居場所となり、成長を支えるための取組みを進めています。中高生世代にとって魅力的な図書館を目指し、探求したいトピックを自由に選べるよう様々なジャンルの図書を充実するだけでなく、中高生世代も利用可能な閲覧および学習用の席やソファー等を居場所として提供することで、図書館がゆっくりと時間を過ごせる居心地の良い場所になるよう努めていきます。
令和7年(2025年)度は、中央図書館、烏山図書館、上北沢図書館の3館で試行的に閲覧席を増設するほか、改築後の梅丘図書館にも中高生世代向けのスペースを用意するなどして、この取組みを推進していきます。
次に、生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・生活支援の拠点事業 「まいぷれいす」についてです。
複合的困難を抱え、支援を必要とする家庭の中学生を対象に、生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習・生活支援の拠点「まいぷれいす」を先行して開いた烏山地域に加え、今年度より玉川地域でも開設し、現在区内2カ所で実施しています。
令和3年(2021年)8月から昨年12月末までに、のべ約8,700人の中学生が利用していますが、安心して過ごすことができる居場所で、個々の状況にあった学習や、信頼できる大人や同世代の子どもとの関わりなどを通じて、自信をつけ、将来について考え始める子どもたちの姿があります。
「まいぷれいす」という愛称には、利用する子ども一人ひとりが、自分の居場所と感じられる空間で、自ら生きる力を育むことができるように、という思いが込められています。引き続き、子どもの健康と自立のために、児童相談所、子ども家庭支援センター、学校等と連携しながら、支援をしてまいります。
次に、施設使用料等の改定についてです。
昨今の物価高騰により施設の管理運営にかかる経費が増加していることを背景として、区民会館、スポーツ施設などの施設の使用料・利用料金を改定します。
公の施設には、区民の皆様の健康増進やコミュニティの創出など、それぞれに設置目的があり、これらの施設機能を将来に渡って維持するため、改定するものです。
区民の皆さんが、物価高騰の影響を受けている中で、区民利用施設の使用料等を改定することについては、様々なご意見を頂きました。
区の直面する課題についても、充当する財源が欠かせず、多面的な検討を加えました。
今回の改定案の検討にあたっては、区民生活への影響に配慮し、急激な改定とならないよう、改定率の上限を3割と設定するほか、高齢の方、障害のある方、18歳以下の子どもの利用について、改定率や改定方法に応分の配慮を行ないました。また、今後の施設運営にあたっては、さらなる経費削減やサービス向上にも併せて努めてまいります。
改定後の使用料等は、一部施設を除き、令和7年(2025年)10月から適用されます。区民の皆様にとってより一層魅力ある施設となるよう、引き続き取り組んでまいります。
次に、防犯対策についてです。
区では、24時間安全安心パトロールをはじめとした各種防犯対策や、様々な広報ツールを活用した区民への注意喚起、地域住民や事業者による見守り活動等を促進し、犯罪の未然防止に取り組んでまいりました。
しかしながら、区内犯罪の発生件数はコロナ禍を経て増加に転じ、令和6年(2024年)の特殊詐欺の被害額は約22億8,000万円となるなど、被害が拡大しています。また、令和6年(2024年)8月以降、SNSやインターネット掲示板などで実行犯を募集するいわゆる「闇バイト」による強盗事件等が相次ぎ、大きな社会問題となっており、区民の危機感も高まっています。
こうした状況を踏まえ、令和7年(2025年)度当初予算に、犯罪を未然に防止するための住まいの防犯対策サポート事業として、約2億円を計上いたしました。この事業は、住宅への防犯カメラ等の防犯設備や防犯フィルムやセンサーライト等の防犯物品の購入に対して、その費用を補助するものです。
また、町会・自治会等の防犯カメラ設置の要望を実現できるように、事業規模を拡大いたします。
次に、遺贈についてです。
ご自身の財産を、亡くなられた後に、後世に役立てる手段として注目されている「遺贈」ですが、今年度、区は4件、約6億8,000万円を頂きました。住み慣れた地域で活かしてほしいという故人の思いを、区としてしっかりと受け止め実現したいと思います。
区ではこれまで、ふるさと納税の取組みを中心に、「児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金」や「医療的ケア児の笑顔を支える基金」など、多くの共感を得るプロジェクトを実現し、寄附文化の醸成に努めるとともに、環境整備に取り組んできました。一方で、遺贈については、相続や遺言など専門的な知識が必要なこともあり、区民の方からのご相談に十分お答えできていない部分がありました。
このような課題に対し、今般、金融機関からのご提案を受け、区内に支店を持つ合計8つの信託銀行、銀行、信用金庫と、「世田谷区への遺贈希望者に対する連携に関する協定書」を締結しました。区への遺贈を考えている方はどなたでも、協定金融機関の窓口で相談が可能となり、必要に応じて遺言信託業務や遺言作成を行う法人の案内などのサポートを受けることができます。
ご自身の財産を住み慣れた地域で育つ次の世代につなげたいという思いを、区として着実に受け止めることができるよう、寄附しやすい環境の整備に引き続き取り組んでまいります。
次に、「ふるさと納税を活用したクラウドファンディング」による新たな市民活動支援についてです。
これまで、市民活動支援事業として、NPO等の市民活動団体あるいは区からの提案に基づき、市民団体と区が公共サービスの提供や地域の課題解決について協働して取り組む「提案型協働事業」を、限度額を50万円とする補助制度により実施してきました。
令和7年度からは、更なる地域課題や社会的課題の解決を図ることを目的に、これまで対象としてきた市民活動団体のみならず企業等も対象に加え、また、目的達成のための資金調達の手段として、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの手法を盛り込んだ、新たな「課題解決事業」を実施します。
このクラウドファンディングにより、市民活動団体や企業等が自ら主体となって、区民からの理解や共感を得ながら、目標金額の設定やそれに基づいた課題解決への取組みを進めるとともに、事業が長期的に継続して行える仕組みを目指してまいります。
また、区民の皆様にも、寄附という形で地域の課題解決等を実感していただくとともに、この新たな取組みを通じて、区内の活動団体をはじめ、企業、区、区民が一体となった市民活動を一層活発にしてまいります。
次に、世田谷区一般廃棄物処理基本計画についてです。
清掃事業が区に移管されて25年が経ち、清掃行政を取り巻く環境も大きく変化し、地球温暖化やプラスチックの処理、食品ロス削減など様々な課題に対応していくことが求められています。区内のごみの排出量は、コロナ禍に一時的に増加しましたが、その後減少傾向に転じています。今後もこの傾向を維持していくためには、持続可能な形で資源を循環的に有効利用するサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が必要です。
この一環として、区では、新たに、プラスチックの分別収集と再資源化、不燃ごみの全量資源化などに取り組むこととしました。区民・事業者との協働により、社会全体の行動変容と意識醸成を促進し、資源循環型社会の実現を目指してまいります。
また、東京二十三区清掃一部事務組合においても、今後10年の清掃工場の整備計画などを策定するタイミングを迎えています。清掃工場の建替えには、巨額の経費と数年間にわたる時間を要し、二十三区の清掃事業とも密接に連動しています。今後、他区とも協力して具体的な検討を進めますが、これを契機として東京二十三区清掃一部事務組合の経営のあり方や、さらなる経営改革についても、議論を提起していきたいと考えています。
次に、世田谷区立学びの多様化学校(不登校特例校)等基本計画(案)についてです。
教育委員会は、学びの多様化学校について、先に基本構想を決定し、具体化を進めてきましたが、このたび旧北沢小学校跡地において、令和8年(2026年)4月に新校を開設する計画案を取りまとめました。
この新しい学校は、学びの多様化学校(不登校特例校)を中心に、心理的要因などで不登校となっている児童・生徒のための心の居場所として支援を行う「ほっとスクール」、さらに、地域の児童の、放課後の居場所・遊び場である「きたっこ」を併設します。「きたっこ」では、地域の児童の利用に重点を置きつつ、多様化学校を含む中学生の利用や、乳幼児が安心して遊び、保護者の仲間づくりの機会を提供する取組みも行います。
このように、乳幼児から中学生まで多世代の子どもたちの居場所や学びの場となるよう、校庭や体育館といった施設を譲り合いながら有効活用することを想定しており、全国的にもたいへん珍しい子どもの学びと育ち、遊びの事例となります。
中心となる学びの多様化学校は、不登校生徒に向け、登校するという結果のみを目的とするのではなく、生徒が自らの将来を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指します。そのため、一人ひとりの生徒の現状や個性に合わせた多様な学びを行うこととしています。さらに、この学校一校にとどまらず、世田谷区の全学校に広めることで、令和6年(2024年)度からの新たな教育振興基本計画の教育目標である、「幸せな未来をデザインし、創造するせたがやの教育」の実現に向け、教育委員会とともに取り組んでまいります。
次に、教員の働き方改革についてです。
私はこれまで、学びの質の改革を主軸に、議論を進めてきました。さらに教育の質を高めていくためには、学校現場の教員が事務作業に充てる時間を減らし、子どもたちと向き合うことができる体制をさらに整えていくことが必要です。
区として、この方向性をはっきりと打ち出し、教育の質を変えていくため、この度、令和7年(2025年)度からの4か年の計画として、「学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン」の案を取りまとめました。
本プランにおいては、教員アンケートなどを通して現状の課題から見えてきた「業務負荷増加のサイクル」から脱却し、「業務負荷軽減のサイクル」に転じることを目指します。7つの基本的な考え方のもと、「小学校高学年における教科担任制の導入及び新人育成・緊急対応の強化のための区独自教員の配置」や「配慮を要する児童・生徒への支援の拡充」、「学校徴収金事務の負担軽減」などの特に教員の負担感が高い業務に関する7つの取組みを「緊急対策プラン」として実施してまいります。さらに、4年間の計画期間の中で、全部で27の取組みを計画的かつ着実に推進してまいります。
次に、インクルーシブ教育ガイドラインについてです。
すべての子どもが共に学び、共に育つ環境の実現を目指すためには、インクルーシブ教育の推進が必要です。
これからの社会は、年齢や性別、互いの違いにこだわらず、フラットな関係で助け合い、お互いの違いを乗り越え、得意なことを持ち寄り、課題を解決していく。これこそが必要であり、まさに教育の基礎であります。教育委員会では、このような考え方を実践し、インクルーシブ教育を1歩ずつ進めるために、「インクルーシブ教育ガイドライン」を3月に策定する予定です。
本ガイドラインは、教員が目の前の子どもたちの状況をどのように捉えればよいかを考え、行動につなげることができるようにするために作成しており、基礎知識や基本理念、教育委員会の基本方針や5つの重点取組み、学校現場における5つの行動コンセプト、それらを教員が実行につなげていくための事例を掲載していくものです。
教育委員会及び学校の体制強化を行うとともに、ガイドラインを教員及び支援員に一人一冊配付し、福祉の専門家等と連携して職種や職層に合わせた研修を行いながら、学校現場の変革に取り組んでまいります。
次に、「世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画」についてです。
インクルーシブ教育を推進し、子どもたちが地域の学校で学ぶことを基本としていくためには、居住する地域に多様な学びの場を確保することが必要です。
新たな特別支援学級の設置を進めることは、通学の負担の軽減や既存の特別支援学級の狭あい化の解消、および特別支援学級で培われた指導方法の校内での共有による教員の指導力向上につながります。
そこで、特別支援学級を希望する児童・生徒が増えている現状をふまえ、このたび、「世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画」を取りまとめました。
計画では、令和7年(2025年)度から9年(2027年)度にかけて、小学校に知的障害学級を3校、自閉症・情緒障害学級を7校、中学校に知的障害学級を3校、自閉症・情緒障害学級を2校、合計15校の学校に特別支援学級を開設することとしました。
児童・生徒が地域の学校で共に学び、共に育つことを目指して、計画に基づき整備を進めてまいります。
次に、令和7年度当初予算案についてです。
一般会計の予算規模は3,996億1,700万円、前年度に比べ7.6%の増となっております。歳入につきましては、特別区税は、ふるさと納税の影響を見込む一方で、賃金上昇・人口動向に伴う増収や国の定額減税の終了に伴う増を見込み、前年度比で126億円の増を見込んでいます。また、特別区交付金は、財源である市町村民税法人分の増等により、前年度比で49億円の増を見込んでいます。
歳出につきましては、大規模自然災害への備えや公共施設の改築・改修経費など、様々な行政需要に対応するとともに、国の制度改正等による児童手当などの扶助費の大幅増や、現下の物価・人件費高のなか適切な価格転嫁を行うなど、必要な予算を計上しております。
一般会計に4つの特別会計を合わせました予算額の合計は5,868億6,800万円、前年度比で4.9%の増となっております。
次に、令和6年度補正予算についてです。
令和6年度の一般会計第7次及び3つの特別会計の補正予算ですが、社会保障関連経費の増や、人事委員会勧告に基づく職員人件費の増をはじめ、事業進捗等を踏まえた経費の増減、公共工事の前倒し等を行うため、合計175億7,800万円の補正予算を計上するものです。
最後に、本議会にご提案申し上げます案件は、令和7年度世田谷区一般会計予算など議案93件、諮問1件、報告1件です。
何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご議決賜りますようお願いしまして、ご挨拶とします。
関連リンク
お問い合わせ先
世田谷区
電話番号 03-5432-1111
ファクシミリ 03-5432-3001